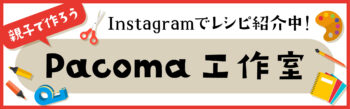- 津久井 玲子
- 自分が仕事の中で勉強したことを、わかりやすさ、伝わりやすさに気をつけて書いています。読んでくださった方にとっても、読んでよかった、勉強になったと思える記事を目指しています。

ピーマンにつく害虫~特徴と駆除・予防方法を解説~
ピーマンは家庭菜園初心者向けの野菜として、とても人気のある野菜です。丈夫で育てやすく、収穫量も多い優良野菜ですが、害虫がつくことも。 本記事では、ピーマンにつく害虫とその種類、対処法についてまとめました。 これからピーマンを育てるという方、ピーマンを育てていて害虫被害に悩んでいる方、ぜひ参考にしてください。
ピーマンの害虫による被害を防ぐには?
ピーマンは家庭菜園初心者でも育てやすいだけでなく、収穫量も多いことから人気の野菜ですが、うっかりしていると害虫がついて、枯れてしまうことがあります。しかも収穫間近の実にも害虫はつくため、実際には気が抜けません。
ピーマンにつく害虫の種類と対処法を、害虫がつく部位ごとに解説していきます。
葉や茎に付く害虫

ピーマンの葉や茎につく害虫を放っておくと、ピーマンの株が弱って成長が鈍くなったり、病気にかかりやすくなってしまいます。そのため、葉や茎に付いた害虫は駆除しなくてはなりません。
ピーマンの葉や茎につく主な害虫には、
- アブラムシ
- コナジラミ類
- カメムシ類
- アザミウマ類
- ヨトウムシ類
- ダニ類
などがいます。
ぞれぞれの特徴と対処法を見ていきましょう。
アブラムシ
アブラムシは、ピーマンの芽や若葉、つぼみや葉の裏などに集団で寄生する害虫です。アブラムシは汁を吸い取るため、アブラムシがピーマンの芽や若葉、つぼみや葉の裏につくと葉や実の形が悪くなったり、黄色く変色し、ひどい場合には枯れてしまうことも。汁を吸うときにウイルスを媒介してモザイク病を発生させたり、排泄物を通してすす病を発生させることもあるため、早めの駆除が必要です。
アブラムシ対策には、殺虫剤の散布をはじめ、防虫ネットでピーマンを覆ったり、黄色い捕虫テープをピーマンの上に吊るしたりすることが有効です。また、シルバーマルチやアルミホイルなどの銀色のシートを敷いておくと、アブラムシが寄り付きにくくなるとされています。
コナジラミ類
コナジラミ類は、主に葉の裏側や芽の先などに寄生して、ピーマンの汁を吸う寄生虫です。寄生された葉が白く色抜けするのが特徴で、葉を手で払うと、まるで白いホコリが舞うように飛び立ちます。被害が広がると光合成ができなくなり、ピーマンの成長が止まってしまうのはもちろん、ウイルス病を媒介したりすることもあるため、危険な害虫です。
コナジラミ類の被害が拡大するのを防ぐためには、ピーマンの周りの雑草を抜き、抜き取った草もすべて処分しなくてはなりません。シルバーマルチなどを敷いて下から反射した光が当たるようにすると、集団飛来を防ぐことが可能。防虫ネットや黄色い捕虫テープも効果があるので試してみてください。
カメムシ類
カメムシ類は、アブラムシやコナジラミ同様に、集団で新芽や茎から汁を吸う害虫です。栄養を取られたピーマンは、ひどいと株全体がしおれて成長が止まってしまいます。せっかくついた実が被害にあうこともあるため、気付き次第捕まえて処分しましょう。
予防方法は周囲の雑草を抜くことです。雑草から移ってくることが多いため、除草を徹底すると被害を減らせます。このほかにも目合いが1mm以下の防虫ネットを張ったり、農薬をまくのも有効です。カメムシを捕まえるときに臭いが気になる方は、ガムテープを使うとよいでしょう。
アザミウマ類
アザミウマ類は、葉に集団で寄生して汁を吸う害虫です。被害にあった葉は小さな斑点状に色が抜けてしまうのが特徴で、被害が広がると、葉が変形して縮れてしまい、落葉するなど成長にも大きな影響が出るため注意が必要です。実の元となる子房にも被害が出ると、ケロイド状の傷がついて見栄えが悪くなります。
傷のついた実を食べても害はありませんが、間接的にウイルス病を媒介するため防除することが大切です。周囲の雑草から移らないよう除草を行い、網目が0.4~0.8mmほどの赤や黒の防虫ネットをかけることや、光の反射を嫌うため、シルバーマルチを敷くのもおすすめです。それでも発生した場合は農薬で除去してください。
ヨトウムシ類
ヨトウムシ(夜盗虫)とは、ヨトウガという夜行性の蛾の幼虫です。
孵化したての幼虫は葉の裏に集団でつき、葉の表皮を残して食害するため、葉が透けて見えるようになります。成長するにつれて葉に穴を開けながら食い尽くし、ぼろぼろにしてしまうため、早めに駆除しましょう。
ヨトウムシを防ぐためには、剪定した枝や葉、枯れた植物を処分することや目合が4mm以下の防虫ネットを設置することが有効です。また、性フェロモン剤を使用することもおすすめです。ヨトウムシは、老齢になると日中、作物の足元の地際にもぐりこむため、殺虫剤はヨトウムシが若い時期、葉に寄生している時期に使用するようにしましょう。また、ヨトウムシは葉の裏に黒や白の卵をまとめて産みつけるので、みつけたらすぐに葉ごと取り除いて処分することもおすすめです。
ダニ類
ダニ類はハダニ類とホコリダニ類とに分けられますが、ハダニ類は葉の裏に寄生して汁を吸い、ホコリダニ類は若い葉や芽に寄生して汁を吸う害虫です。発生したばかりではいずれもわかりにくいですが、増殖すると葉が委縮したり巻いた状態になるなど、形が変形します。
ひどくなると葉が落葉し、芽が伸びない芯止まり状態になってしまうため、農薬をまいて早めに駆除するようにしましょう。雑草から移ってくることが多いため、雑草が生えにくいよう防草シートを敷いたり、除草を徹底すると効果的です。
また、ハダニは水を嫌う性質があるため、散水して湿度を一定に保つと寄り付きにくくなります。ただし、過湿しすぎると蒸れて病気の原因にもなるため、作物や土の状態を見ながら、水をまくタイミングや量を調節してください。
カイガラムシ類
カイガラムシ類は、カメムシの仲間に分類される昆虫で、ピーマンにはマデイラコナカイガラムシやナスコナカイガラムシなどが発生します。白色粉状のロウ物質で覆われる体長5mm以下の小さな害虫ですが、排泄物にすす病が発生し、多発すると生育不良を引き起こします。
カイガラムシ類の被害を防ぐためには、雑草を抜き、きちんと処分することが重要です。また、体がロウ物質で覆われていて、大きくなると薬剤をはじくことから、薬剤を散布する際はロウ物質で覆われる前の時期に行うことがポイントとなります。
果実に付く害虫

葉や茎につく害虫の多くは果実にもつきます。そのため、葉や茎だけでなく、果実にも同じように注意を払い、防除するようにすることが大切です。
果実につく害虫には
- タバコガ類
- アザミウマ類
- アブラムシ類
などがいます。
アザミウマ類・アブラムシ類は葉や茎につく害虫の部分で解説しているので、ここではタバコガ類について見ていきましょう。
タバコガ類
タバコガ類とは、蛾の一種で、幼虫が実に穴をあけて潜り込み、主に種を好んで食害します。幼虫そのものの数が少なくても実から実へと渡り歩くため、幼虫の数以上に被害が出やすい点が特徴です。実に直接被害を与える害虫のため、収量に直結する厄介な害虫といえます。
タバコガ類の対策に有効なのは、穴の開いた実を見付け次第、摘み取って処分すること。摘み取った実の中に幼虫がいない場合、周りの実に移っている可能性があるため、周りもしっかり調べましょう。
薬剤は、幼虫が実の中に入ってしまってからでは効果が期待できないため、幼虫が実に入り込む前に散布することが大切です。
また、産卵されるのを防ぐために防虫ネットを設置したり、窒素過多とならないよう、肥料を控えることも有効です。
根に付く害虫

ピーマンの根にも害虫はつきます。上から見ただけでは被害が出るまでわからないため、より注意が必要です。被害の出方を見極め、早めの対策で防除しましょう。
根につく害虫には
- コガネムシ類
- センチュウ類
がいます。
それぞれの特徴と対策について解説します。
コガネムシ類
コガネムシ類というと、楕円形で光沢のある成虫を思い浮かべる方が多いと思いますが、コガネムシ類の幼虫の多くは、白く、土中に生息します。
この幼虫は根を食害するため、ピーマンの苗の成長期に当たる育苗期に被害を受けると成長できず、せっかくの苗が枯れてしまうこともあります。株が急激にしおれてきたら、コガネムシの害を疑ってみましょう。
コガネムシが好むのは、柔らかく、腐食質に富んだ土。つまり、有機農法を目指して腐葉土を多く入れすぎると、逆にコガネムシを呼んでしまうことがあるため、対策をしっかりとることがおすすめです。
コガネムシに対する対策として、
- 畑の周辺に成虫が好むクリやブドウなどの木がある場合には農薬を散布して成虫を減らす
- ピーマンの苗の根元をマルチシートで覆うことで成虫に卵を産みつけられるのを防ぐ
という方法があります。
マルチングを行う時期は、産卵期を迎える6月以前が効果的です。
それでも被害が発生してしまったときは、根元を掘り起こして幼虫を駆除してください。
センチュウ類
センチュウ類とは、その名のとおり、細長いひも状の身体をした害虫のこと。土壌の中に膨大な数がいるとされています。
このセンチュウ類が根に寄生すると根がコブ状になり、多発すると葉や茎がしおれて全体が黄色味がかり、成長が止まります。
根に寄生するため発見しづらいことから、ピーマンの種をまいたり苗を定植したりする前に、土壌を消毒するなどの予防が重要です。土壌の消毒は、たっぷりと水をまいてから透明のポリマルチシートを隙間なくかぶせて、20~30日放置するだけで完了。太陽熱でしっかり土壌を消毒することができます。
このほか、ピーマンやピーマンと同じナス科の作物を栽培した場所で連作しないことや畑やプランターの土を入れ替えることも有効です。
害虫はウイルス病の媒介も!

ピーマンにつく多くの害虫は、葉や茎から汁を吸う際に、ウイルスを媒介することがあります。また、排泄物にカビなどが生えたりして、さまざまな病気を蔓延させる原因になることも。中でも怖いのがウイルス病で、かかったら最後、株を抜いて処分するしかないものも珍しくありません。
ピーマンは育てやすい野菜ですが、水やりのときなどに株全体を見回し、葉の裏にも異常がないかを確認して、害虫がついていたら早めに対策するようにしましょう。害虫に対して早期に対策をすれば、美味しい実をたくさんつけてくれるはずです。
おわりに
ピーマンにつく害虫の中には最終手段の農薬にも高い抵抗力を持つものもいます。そのため習性を利用した防除方法で防ぐのが理想です。適切に害虫対策を行って健康に育ったピーマンは、きっと豊かな実りで応えてくれることでしょう!