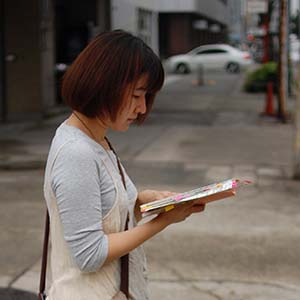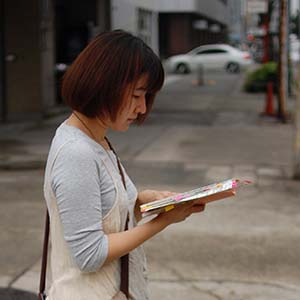
- 岩本恵美
- フリーランサー(編集・執筆、たまに翻訳)。
東京・下町生まれの下町育ち。Webメディアや新聞記事の編集・執筆を経て、フリーランサーに。経済からエンタメまで、気になったら何でも手を出す雑食系。ここ数年は盆踊りにハマっています。

「確定拠出年金はメリットだらけ!」なんて言葉が信じられないという人へ。確かに確定拠出年金はメリットだけではなく、デメリットも存在します。基本的な情報から、確定拠出年金の素朴な疑問をプロに答えてもらいました。

1972年生まれ。中央大学法学部卒業後、企業年金研究所、FP総研を経て独立。老後に向けたお金作りのアドバイスが得意。投資教育と確定拠出年金の専門家でもある。マンガやゲーム、アニメ好きといったオタクFPの一面もあり、マンガの蔵書は約4000冊。

まずは確定拠出年金の基本を知りましょう。「企業型」「個人型」の種類、それぞれのメリットとデメリットを見ていきます。
確定拠出年金には、企業型と個人型(iDeCo)の2種類があります。
企業型は勤め先の会社が導入していないと入れませんが、個人型確定拠出年金は2017年1月の法改正で現役世代の人たちは誰でも入れるようになりました。
それぞれの主な特徴は以下のとおり。どちらも運用方法は個人が責任を負うことになっています。
企業型確定拠出年金のメリットとデメリットについて紹介します。
個人型確定拠出年金のメリットとデメリットについて紹介します。

「私は確定拠出年金に入るとメリットとデメリットどちらが大きい?」と確定拠出年金に加入を悩んでいる方必見! 確定拠出年金のプロ、FPの山崎俊輔さんがあなたの疑問にお答えします。
もし勤め先で企業型確定拠出年金をやられている場合は、原則として個人型確定拠出年金には加入することはできません。ただし、会社によっては「マッチング拠出」を導入している場合があり、企業型確定拠出年金に個人負担で掛金を追加することができます。個人型の確定拠出年金とほぼ同様の税制優遇が受けられるので、会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
専業主婦の場合、課税所得がそもそもありません。つまり、所得税や住民税が軽減されるという個人型確定拠出年金の税制上の大きなメリットがないわけです。たとえ実態は旦那さんが掛金を支払っているとしても、税制優遇は加入者本人のみが対象となるので、旦那さんの所得控除として計上することはできません。
ただし、受け取り時には、会社に勤めていなくても加入期間=勤続年数として退職所得控除を活用できるというメリットはあります。
とはいえ、一般の会社員と比べると節税効果は少なくなるので、じっくり検討してみることをおすすめします。
結論から言うと、NISAよりも個人型確定拠出年金(iDeCo)を優先すべきですね。NISAは投資利益が非課税になるもの。一方、iDeCoの節税効果は拠出時、運用時、受け取り時の3段階で発揮でき、税制優遇が強いです。ただ、iDeCoは60歳まで引き出せないので、マイホーム購入資金や子どもの教育費として60歳前に資金が必要ということであれば、NISAを併用するのも一つの手です。
どんなものにメリットとデメリットはあるもの。確定拠出年金もメリットとデメリットをきちんと理解した上で活用すれば、メリットを最大限に活かすことができるはずです。知らないことは損なので、しっかり勉強して自分に必要なものなのか、見極めてみてください。